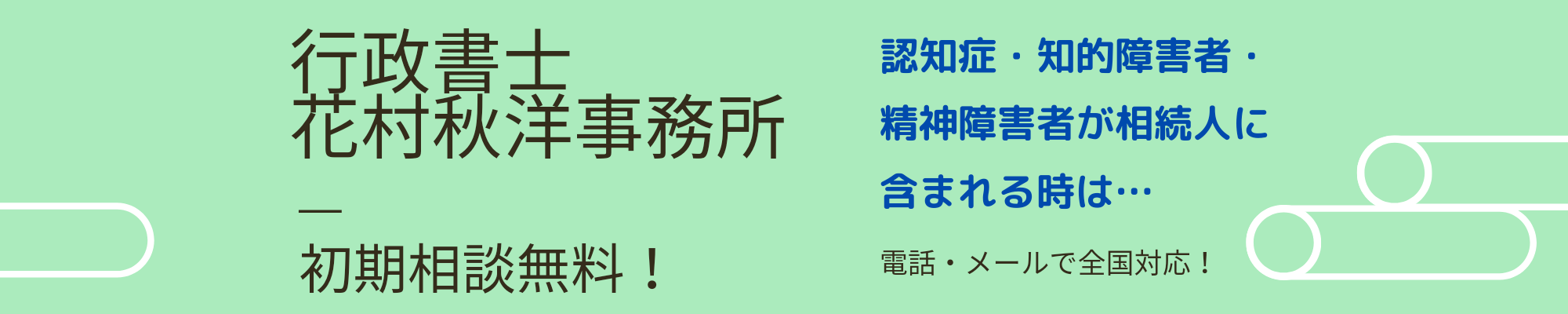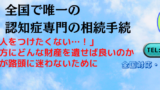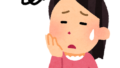知的障害者入所施設ではどのような取り扱いをしているのか気になる点を「家族目線」で聞いてみました!
知的障害を持つ方のご家族としては、自分達がいなくなった後、入所施設で生活を送ってもらうことを希望されることが多いと思います。
入所までの手続きなどは行政や福祉機関で聞くことはできると思いますが、実際の運営や取り扱いに関することは行政も知りませんし、HPに載っているものでもありません。
今回は、おそらく初公開になろうかと思われる「知的障害者施設の実際」について4つの入所施設の施設長に聞いてみたことを公開したいと思います。
貯金はどれくらい必要?障害年金だけで生活は送れるのか?
まずは利用者の生活にかかるお金についてです。
入所施設に入る知的障害の方は、ほとんどの方が障害年金を受給していると思います。

毎月の障害年金だけで施設生活を継続して送れるのかについては、親目線では最も気になる点の一つだと思います。
障害年金だけで足りないのであれば、入所するまでに貯金をしておかなければなりません。
もちろんお金が無くなっても生活保護を受給できれば施設生活を継続できますので、その点は安心しておいて良いかと思います。
ただし、今回聞けた中ではグループホーム(社会福祉法人運営)は一か所でしたので、民間(株式会社等)が運営するグループホームなどでは、必要な費用が変わってくる可能性があります。
将来の入所施設を検討する際は、費用についてもあらかじめよく聞いておくことが必要です。
4施設とも「YES」!障害年金のみで毎月の生活費全てをまかなえるケースがほとんど!
回答としては、施設での生活費が障害年金の毎月額を超えることは無いとのことでした。
ただし、絶対に超えることが無いという意味ではなく、現状では超えている者はいないが、人によってはあり得るということを含ませていました。
例えば、趣味にお金がかかったり、特別なサービスを受けていたりする場合は、障害年金の額を超えてしまう可能性はあるとのことです。
しかし、通常の生活を送っている限りは障害年金で全て賄えてしまうだろうとのことです。
これはご家族にとっては安心できる情報だと思います。
世間では「障害のある子にはできるだけ貯金を残しておくこと」が常識だと思われていますが、私は必ずしもそうだとは思いません。

なぜなら、障害福祉サービスが貯金を前提にしている制度であるはずが無いからです。
例えば老後には貯金が2000万円必要などという情報がメディアなどで出回っていましたが、これも厳密に言うと嘘です。
貯金ゼロでも生活は送れるように設定されているのが高齢福祉サービスだからです。
もちろん有料老人ホームなどの高価なサービスを利用すればお金は必要です。しかし最低限のサービスを選択すれば、ほとんどの場合老齢年金の範囲内で収まるはずです。
障害福祉サービスでも同じことが言えます。実際にも今回聞いた4施設では障害年金の範囲内で皆さんが生活を送れているということなので、過剰に貯金をする必要は無いというのが分かってもらえたと思います。
障害年金2級だと足りない?
障害年金2級の方は、1級の方よりも毎月の受給額は低いです。
しかし2級に該当する方でも施設生活を送れる可能性は高いということです。
なぜなら、毎月の負担額を調整する制度があるため、障害年金2級の方でも施設生活が送れることが原則となっているからです。
利用者本人のお金の管理はどうしてる?通帳は預けるべき?
入所サービスを利用する場合、利用者本人の、障害年金が振り込まれている口座の通帳を預けている方がほとんどです。
この取り扱いには施設と利用者両者にメリットがあるため、かつてからの通例となっています。
施設としても、毎月の年金が振り込まれる口座であれば残高不足になることはないため、利用者へのサービスを安定して継続できます。
家族としても残高不足により利用者のサービスが停止される恐れもなくなりますし、毎月の費用を口座から引き出してもらえるなら支払いの手間がかかりません。
ただし注意点としては、「多額の入った通帳」を預けることです。
通帳を一旦預けると、本人が施設を利用している間は家族が通帳を使うことはできません。
そのため、家族が任意にお金を下ろすこともできません。
この点については問題になることもありますので、以下の記事を参考にして、トラブルの無いようにしましょう。
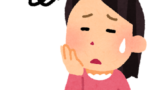
どの家族なら主介護者や身元保証人として認めてもらえる?
当事務所でも常に警鐘を鳴らしていますが、本人の身元保証人としてどの家族なら認めてもらえるのかという点についても聞いてみました。
これについては、「親・兄弟」はもちろんのこと、「いとこ」や「兄弟の配偶者」、「兄弟の子(甥・姪)」までは認めているという現状を教えてくれました。

しかし本人との関係性を重視しているため、本人にほとんど会ったことのないような遠くの親戚が身元保証人となることについてはどの施設も懸念があるようです。
もちろん身寄りが無い場合は、成年後見を申し立てた上で本人が継続して施設を利用できる余地がありますので、あまり無理せずに家族の負担にならない方法を考えるべきだと思います。
現在成年後見人が就いている利用者の割合は?
これも気になる方は多いと思いますが、これは施設によりバラバラでした。
3施設では「1割弱〜1割強」でしたが、1施設では「3割〜4割」という非常に高い割合でした。
障害者の高齢化に伴い、今後は増加していくことが見込まれます。
親が突然亡くなった場合はどうなるの?
今まで親が身元保証人になっていたが、急に亡くなってしまったらどうなるのか?ということも聞いてみました。
親としてはその後のことは知ることもできないため、大変不安に思っている方も多いでしょう。
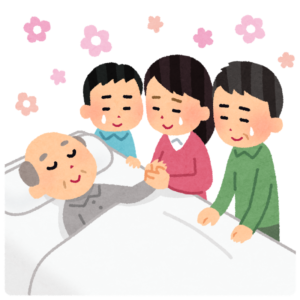
これは必然的とも言えるのですが、施設としては「家族で見れる人を探し、いなければ成年後見(行政経由)」という流れにするそうです。
行政に相談することにより「市町村長申立」にて成年後見人をつけてもらえれば、施設としても継続的に施設サービスを提供できますが、自治体もすんなりと市町村長申立を行ってくれるケースは少なく、施設としても困っているという現状を聞いたことは以外でした。
親が亡くなってしまった後にもスムーズに施設生活を継続できるよう、親が生前のうちから先のことを考えておくことが重要だと思います。
まとめ【入所サービスの利用については必要以上に不安に思わないこと!】
実際に多くの施設の現状を聞ける機会というのはほとんどないため、今回の情報は非常に貴重なものだと思います。
しかし、施設の現状を聞いて考えたことは、「過剰に不安に思うことは無い」ということです。
お金についてもほとんどの場合障害年金以上の費用がかかることは無いですし、万が一お金が足りなくなっても生活保護の受給に移れば、本人の生活の質がそれほど下がることはありません。
また親が亡くなった場合も、施設としては他の親族に協力を求めますし、誰も身寄りがいなければ市町村長の申立を求めてくれます(施設としてはかなり大変なようですが…)。
今回取材させていただいた施設でも利用者の皆さんと交流させてもらいましたが、高齢になってもお元気で楽しそうに生活していたのが印象的でした。
それでも、今できる範囲でやっておくべき財産管理や相続対策はあると思いますので、お困りの方は当事務所にご相談いただければと思います。