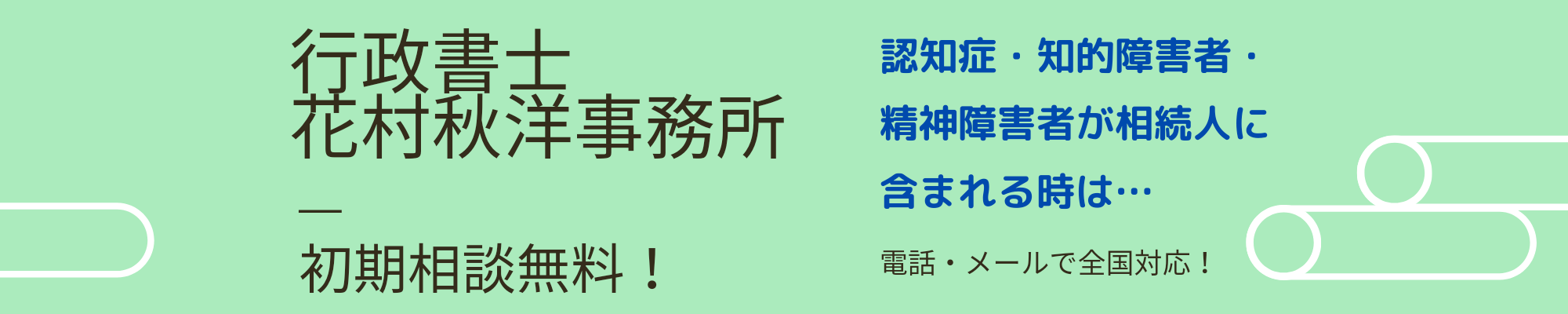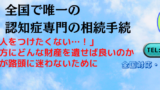勝手に成年後見人をつけられるというケースの多くは「市町村長申立」
当事務所へのご相談の中には「家族の知らない間に勝手に成年後見人がつけられてしまった」という内容が多くあります。
一見するとあり得ないような話ですが、成年後見制度の構成から考えると当然あり得る話なのです。
とはいえ、かつてよりもその件数は増加しており、その理由の一つが「市町村長申立の増加」です。

市町村長申立は、成年後見の申立を行える家族や親族等がいない場合などでも、本人に成年後見人をつけることができるというある意味では便利な制度です。
しかし、市町村長申立は家族や親族がいる場合でも行えます。むしろ家族や親族がいる場合に行われてしまった市町村長申立のほうが問題になっていることがほとんどだと思います。
なぜなら、市町村長申立は家族や親族の意向に反して行われるケースが多いからです。
問題となっているケースの市町村長申立の仕組とは?
それではなぜ家族や親族の意向に反して市町村長申立が行われているのでしょうか?
市町村長申立を行う場合、家族や親族の意向は問いません。むしろ家族や親族に伝えずに行われることに真髄があるのです。
例えば、母(85歳)、息子(60歳)の二人親子がいた場合、息子が母親の預金を使い込んだり、母親に対して暴力を振るっていた場合はどうでしょう?
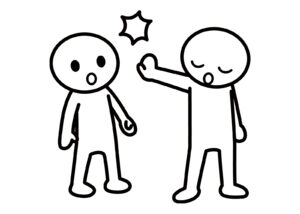
市町村長がそれを知ってしまった場合、本人保護の要請が働きます。
市町村長としては、母を守るために、息子と引き離し、通帳を確保しなければなりません。
母に第三者の成年後見人をつけて、その者に通帳を所持・管理させ、さらに成年後見人が施設と契約して母を施設で生活させることができれば市町村長の目的は達成できます。
これを速やかに行いたい場合、息子の承諾を得ていては難しくなります。息子に知らせることで妨害(母を隠す等)を行うかもしれません。
そのため、市町村長は成年後見人の申立を「勝手に」行うという流れになります。
市町村長申立にあるいくつもの問題点とは?
このように行われる市町村長申立ですが、問題となっている理由がいくつもあります。
スピーディーな本人保護を行うことを重視しているため、明らかになっていない点でも解明せずに行われるということが、この制度のメリットでもデメリットでもあります。
仕方ないと言ってしまえばそれまでなのですが、当事者の本人や家族としては納得できない点が生まれてしまうという理由を、関係機関ごとにいくつか挙げていきます。
事業所・市町村の問題
まず市町村長申立の多くは、福祉機関や病院の相談から始まることが多いです。
先ほど挙げた親子の例で言えば、ホームヘルプサービスを行っている事業者の職員がまずそのことに気付きます。

そして事業者は市町村の担当課に連絡し、その判断を仰ぎます。
なぜここで問題が生じるのかというと、「その事実が本当に行われているか」の判断に100%の根拠が無い場合が多いからです。
高齢者虐待防止法では、「虐待のおそれがある場合」にも以下の通報義務(または通報努力義務)があります。
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
この判断を一介護職員が行うことは非常に困難です。
もちろん事業者全体でカンファレンス等を行い、事業者の責任において市町村に報告することになりますが、ここに差異が生まれてしまうことは明らかです。
例えば仲の良い親子であっても「うるせえババア!」なんて言葉遣いをしてしまう子もいますし(あくまでも私の現場時代の体験上ですが…)、母親が使えないお金を多く持っているという理由で毎月振込を受けている子だっているはずです。
しかしこれらはいずれも高齢者虐待防止法に規定されている虐待に該当する「おそれ」があります。
高齢者が虐待を受けたと「思われる」場合は通報する義務(または努力義務)が生じてしまうのです。
ここは事業者や職員も苦悩する点だと思いますが、高齢者虐待防止法に真摯に対応しようとする事業者であるか、腫れ物に触ることは極力避けたいと思う事業者であるかにより、かなりの差異が生まれていることでしょう。

家庭裁判所の問題
成年後見の申立が行われた場合、家庭裁判所は本人の状況等を把握した上で、成年後見の必要性の判断をしなければなりません。

しかしこの判断もかなり難しい所があります。
家庭裁判所は福祉の専門家ではありません。その裁判所の職員が短期間で本人を取り巻く状況を判断することは非常に困難なのです。
ということは、多くの場合決定的な資料は事業者と市町村側の言い分です。
家族や親族の言い分は聞けません。なぜならこのケースでの市町村長申立は、家族や親族に連絡をせずに行われることが多いからです。
ここで裁判所と市町村長との認識が生じてしまうリスクがあるという制度なのです。
スピーディーに判断をしなければならない。本人や家族から状況を聞けない。結果、ある程度曖昧な点があったとしても成年後見人等をつける判断を取らざるを得ないという状況になってしまうのは、制度上仕方が無いとも言えます。
どうしても成年後見人をつけられたく無い場合に取れる手段!
ということで、市町村長による成年後見の申立という制度には、まだまだ問題はありつつも、良い解決策は無いように思えます。
スピーディーな本人保護が第一優先であるため、事業者や市町村、家庭裁判所もある程度のリスクを負いながらも成年後見人等をつけることに進まざるを得ないのです。

それでは、家族が取れる手段は無いのでしょうか?
実はあります。
というのも、今までの虐待を理由とされた市町村長申立は、家族がこれを守っていれば半分以上は行われなかったのではないかと思っているからです。
成年後見を語る多くの専門家は法律の専門家です。また福祉の事業者は成年後見に関する知識や経験はほとんどありません。
私が考える家族の取れる手段とは、長年の福祉現場での経験を元に、今まで多くのご相談を受けてきた当事務所が考えた結論になります。
勝手に成年後見人をつけられないためには「事業所の言いなりになる」!
言い方は悪いですが、核心を突く短い言葉はこれしかないと思います。
もちろん家族による虐待があってはならないのはもちろんです。通報の対象となるような虐待行為やそのおそれがあると判断されてしまうような行動は絶対に行ってはいけません。

家族間では理解し合えていることだとしても、事業者の前では疑われないようなコミュニケーションを取ることが第一です。
そして次の事項も重要です。
私が相談を受けてきたケースのほとんどが「家族と福祉サービスの事業者の折り合いがついていない」という状況でした。
支援サービスについての細かい説明を求める、本人の支援指針の違い、訴訟をちらつかせる、利用料の滞りなどで、事業者と家族の間でトラブルが起こすことは非常に危険です。
例えば、対応に過度の負担がかかってしまう家族がいたとしましょう。

事業者としては、その家族とやり取りをするより成年後見人とやり取りをする方が楽なのです。
もちろん簡単には市町村長申立は行えませんが、明らかに事業者側は成年後見人をつけたほうが得なケースというのがあるわけです。
考えたくはないですが、相談を受けている中ではそのような思惑もあるのではないかと疑ってしまうケースもあります。
ということで、一番のリスク回避は「事業者側の望む品行方正な利用者とその家族」でいることになります。
「こちらはサービスを受ける側だ!」、「人質を取られたようで悲しい!」と考えるのは当然です。しかし私の経験上は一番効果的なのはこれしか考えられないのです。
「事業者の言いなり」具体的には…
私が考える「言いなり」の具体例を以下に挙げます。
- 福祉サービスの内容に過度な説明を求めたり注文をつけたりしない
- 利用料はすぐに支払う
- キーパーソンを明確にし、他の家族はキーパーソンと方針を同一にする(家族間で揉めない
- サービスを終了したいときは事業者の責任を追及する素振りは見せずに穏便に契約を終了する
- (多くは障害者施設)事業者に通帳を預けている場合はその口座からは引き出さない
以上になりますが、とにかく事業者の意にそぐわないことをしないということ、まさに「言いなりになる」という状態です。

家族としては納得できませんが、「良いお客さん」という体を取れば事業者としても恣意的な市町村長申立には動かないでしょう。
もちろん事業者に対して意見を伝えなければならない状況もあります。
その際も、あくまでも丁寧に希望や問題点を指摘するにとどまり、穏便に話ができるように努めましょう。
本当に納得できない場合はサービスをやめるしかないですが、その際は事業者側が悪いからという理由ではなく、こちら側の都合ということを強調しましょう。
市町村長申立は今後も増加していくが予防策は知っておくこと!
市町村長申立の利用状況は今後も増加していくでしょう。
悲しいですが、今回のような内容をリアルに述べているような媒体は無いと思いますので、恣意的な申立を予防するという意味でも、今回の情報を頭の片隅に入れておくと良いのではないかと思います。
※当事務所では「成年後見人を勝手につけられてしまった」という事例には対応できません(対応策はほぼありません)が、遺言や相続手続きによる未然の防止策についての知識や経験は豊富に持っておりますのでぜひご相談ください。