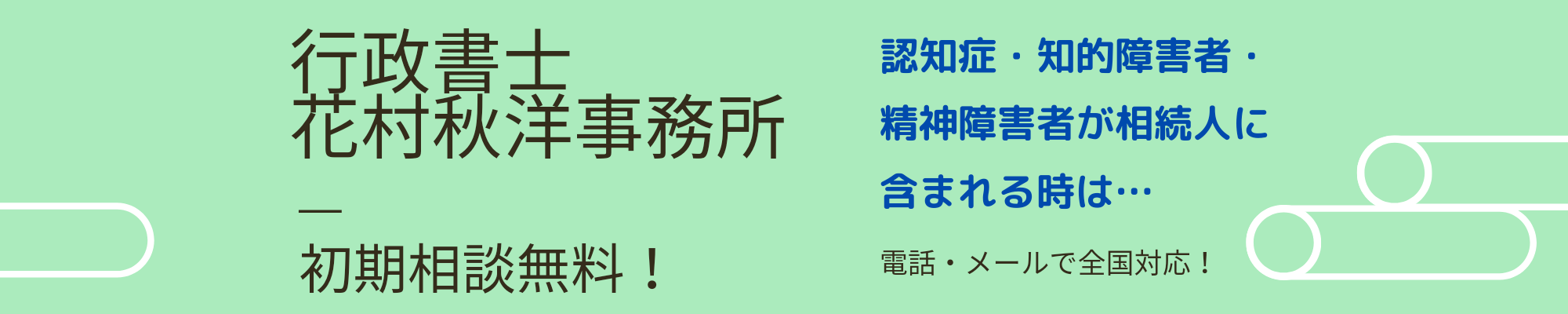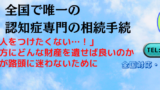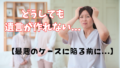重度障害者の相続では遺言が無いと多額の損失が発生する
一般市民の中では、遺言を作り将来に備えているという方は多くはいないと思います。
「みんな作ってないから大丈夫でしょ」
「ウチは揉め事が無いし法律どおりに分ければ良いでしょ」
と思っている方がほとんどでしょう。
確かに遺言が無くても問題がない家庭はたくさんあります。
相続人の中に認知症や障害のある方がいなかった場合です。
法定相続分で分ければ平等であり、問題も特に起きないという家庭が多くを占めていると思います。
しかし相続人の中に認知症や障害のある方がいた場合は話は全く別です。
多額の損失が発生することはおろか、相続手続き自体も困難になってしまうからです。
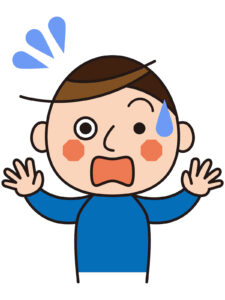
今回は重度障害者が相続人にいる場合の、遺言の有無による損失金額の比較をケースごとにしてみたいと思います。
ケース①:相続財産総額が4000万円の場合
【モデルケース】
父、母、長男、長女の四人家族。長女は重度の知的障害により意思能力が無い。父が亡くなり相続が発生した。

まずは上記のケースで不動産や預貯金を含めた総財産額が4000万円程度の平均的な家庭で考えてみます。
(法定相続分は、母2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。)
遺言が無い場合
金額だけで考えると、母が2000万円、長男が1000万円、長女が1000万円相続します。
しかし長女は施設で生活しており、生活費は障害年金から捻出しているため、特に財産が必要というわけではありません。
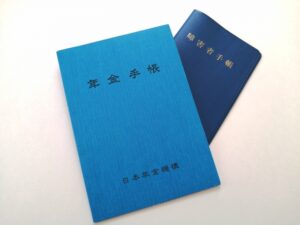
そのため、長女にはお金を渡さず、足の出た場合に家族が補填すれば十分だと考えていました。
しかし実際はそうはいきません。
長女に意思能力が無いと判断されてしまったため、成年後見人をつけないと相続できないと銀行や法務局に言われてしまいました。
遺言が無かったため、結果的には成年後見人をつけて法定相続分通りに相続することとなりました。家と土地は母が住むために必要だったため、母は現金を取得することができず、長男と長女にはそれぞれ1000万円の現金が渡りました。
遺言がある場合
父は生前に遺言を残していました。その趣旨は以下のとおりです。
「母に家と土地、現金1000万円を相続させる。長男に現金1000万円を相続させる。長女には何も相続させない。」

母が遺言執行者に指定されていたため、成年後見人をつけずに相続手続きを終えました。長女には法定相続分の半分となる遺留分があったため、将来成年後見人に請求された場合に返還できるよう、500万円をとっておきました。
遺言の有無による差
実際に将来成年後見人がつくか否か、遺留分を返還するか否かは未確定ですが、返還することを考えたとしても500万円の差が生じました。
さらに遺言がない場合は、成年後見の申立費用も発生します。
長男に子がいる場合であれば長女の相続財産は最終的に相続されますが、長男に子がいない場合は、亡くなる順序によっては長女の財産が国庫に入ってしまうため、500万円が丸々損してしまうことになります。
| 遺言あり | 遺言なし | 差異 | |
| 母 | 2500万円 | 2000万円 | +500万円 |
| 長男 | 1000万円 | 1000万円 | |
| 長女 | 500万円 | 1000万円 | -500万円 |
ケース②:相続財産が一億円の場合
上記同様のケースで、相続財産の総額が一億円だった場合をシミュレーションしてみます。
遺言があれば長女には、本来の相続分の2500円から遺留分の1250万円と低い額を渡せば良いことになります。
そうすると、単純に考えただけで1250万円を有効に使うことができるようになります。
| 遺言あり | 遺言なし | 差異 | |
| 母 | 6250万円 | 5000万円 | +1250万円 |
| 長男 | 2500万円 | 2500万円 | |
| 長女 | 1250万円 | 2500万円 | -1250万円 |
ケース③:相続財産が1000万円の場合
不動産などが遺産に含まれず、総財産が少なめな場合でも、遺言の作成費用を上回る額を得することになります。
当事務所の遺言作成報酬は約20万円、公証役場の手数料が5万円としましょう。
長女に渡る法定相続分は250万円ですが、遺言があれば、遺留分の125万円で足ります。
この場合でも100万円が有効活用できるようになります。
| 遺言あり | 遺言なし | 差異 | |
| 母 | 625万円 | 500万円 | +125万円 |
| 長男 | 250万円 | 250万円 | |
| 長女 | 125万円 | 250万円 | -125万円 |
遺言の価値が最も高い点は「成年後見人をつけずに相続手続きができる可能性がある」ということ!
今回はお金だけで損得を考えてみましたが、障害者や認知症の相続にとって遺言が果たす役割で最も重要なのは「成年後見人をつけずに相続手続きができる可能性がある」ということです。
この価値をプライスレスと考えるご家庭も多いことでしょう。

逆に、遺言が無いために成年後見人をつけることになってしまう家庭がほとんどですので、それを解消できる遺言は、認知症や障害者の方がいらっしゃるご家族では必須のものとなります。
ただし、遺言の内容を間違えるとせっかく作ったにも関わらず成年後見人をつけることになってしまったり、相続税が高くなってしまったりするので、内容をよく吟味しましょう。
当事務所では、障害者や認知症の方が相続人に含まれる場合の遺言作成業務を行っています。
必ず書かなければならない事項や相続税に関しての検討を加えた内容で作成することが必要ですので、遺言の作成をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。