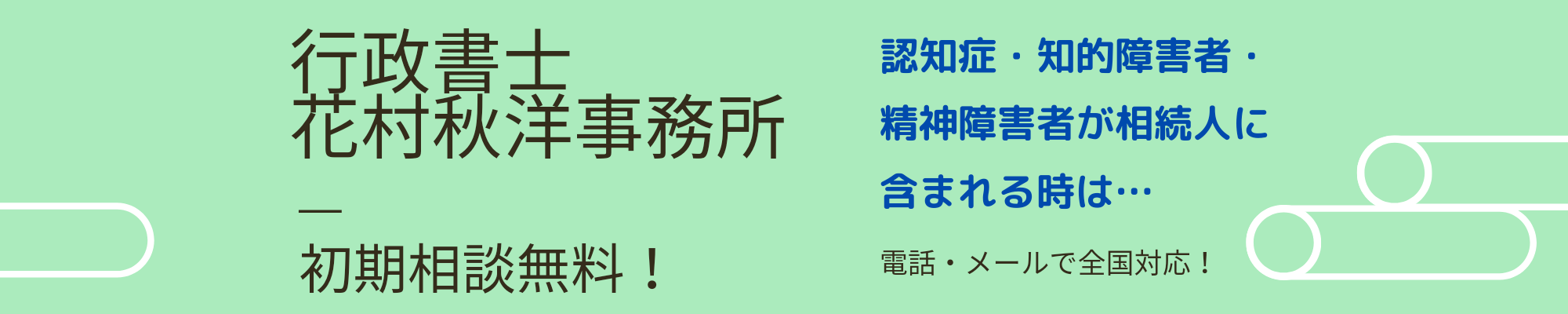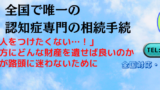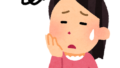相続人不在のため国に入るお金は年間700億円!?
人が亡くなった後、相続人がいない場合はその人の財産は国庫に帰属(国がもらえる)します。
その額は毎年数百億円とも言われ、多い時は700億円を超えることもありました。
もちろん自分が死んでしまえばそのお金がどこに行こうと何に使われようと知る由もありません。
しかしそれはあまりにももったいないと考える人もいると思います。
自分の生涯の財産は自分の意志で帰属先を決めたいと考えるのは当然のことです。
それでもケースによってはそれを定めることが非常に困難になる場合があります。
例えば自分が重度の認知症になってしまってからでは遺言を残しておくこともできません。

今回は、自分の意志で贈与や寄付(遺言による遺贈)を行う方法について解説します。
今までできないと考えられていたケース【障害のある一人っ子がいる場合】
最後の財産はお世話になった施設にあげたいと考えているが、今までどうしてもできなかったケースがあります。
そのケースとは「重度障害のある一人っ子」がいる家庭の場合です。
父が亡くなり、母と子の二人家族となった場面では、どんなにお金があろうと全額を施設に寄付することはなかなかできません。
なぜなら母が亡くなった後は重度障害のある子が一人になるからです。
父から受け継いだ多額の財産が使い切れないほどの額だった場合、子が入所している施設(法人)に寄付したいと考えるのは当然のことです。国が法律どおりに、何の感謝もせずにお金を吸い上げていくということには嫌悪感まで覚える人もいるでしょう。
しかし子が残されているのですから、子が生活に困ってしまうことだけは避けたいと考えます。
そのため、何もしなければ母の財産は子に相続されます。
その後、子が一人になった時に、市町村長により成年後見の申立が行われ、就任した成年後見人がそのお金を管理します。

子が重度障害であった場合、障害年金が支給されているでしょうから、相続財産はほとんど手をつけられず、成年後見人の報酬の支払いのみに用いられます。
子が遺言を作成し、他の者に財産を渡せる段取りが取れれば良いのですが、意思能力がなければ遺言を作成することもできません。
そしてその子が亡くなった際は、全財産を国へ移転する手続きが行われます。
子の生活を保障しつつ贈与&寄付を行う方法!
施設等に寄付はしたいが、子が心配なために行えないとお困りの方は多いと思います。
そのような方のために、当事務所では以下の方法を考え出しました。
これらの方法をとることにより、残されたお子さんの生活を保証しつつ、お世話になったところに寄付をすることも可能になると思います。

以下にパターンごとの方法を挙げていきます。
甥や姪、その他の親族へ贈与したい場合
まずは、相続人では無いが、関係のある(無くても)親族に贈与したいと考える場合です。
この場合、あげたいと思う人に事前に話し合うことが重要になります。
その上で、少々テクニカルな内容の遺言を作成することが必要です。
子の生活を保障しつつ親族に財産を渡す内容の遺言例
まず、遺言執行者をその親族に設定します。
遺言執行者とは、遺言を実現する手続きを行う権限のある者です。

遺言執行者は、遺言に書いてあることを全て単独で行うことができます。
遺言執行者が受贈者(遺贈を受ける者)を兼ねることも全く問題がありません。
そのため、その親族を遺言執行者兼全財産の受贈者とします。
そして、以下のどちらかの内容を加えます。
①(当該親族は)金◯◯円を子(重度障害の)に支払う
②(当該親族は)子の生涯にかかる費用を負担する
子が生涯かかるお金を正確に計算するのは難しいため、②の方法を取る方が国に渡るお金を少なくすることはできます。しかし万が一ということを考え、お金を余らせてしまうくらい渡しておくのも良いと思います。
お世話になった施設や病院(を運営している法人)に寄付したい場合
では、特に財産を渡したい親族もおらず、子がお世話になっている施設や病院にあげたいと考える場合に取れる方法です。
この場合も事前に話をしておくと良いのですが、遺言について何も伝えなくても法的には有効です。
しかし、遺言執行者も受贈者も、遺言の内容を放棄することができてしまうため、自分が亡くなった後に思ったようにならないリスクが残ります。
ただし、遺言執行にかかるコストよりも金額が大きければ、施設や病院にとっても大きなメリットになりますし、亡くなった方の最後の意志を尊重したいと考える施設等のほうが圧倒的に多いと思います。
施設等に寄付することは子にとっても大きなメリットあり!
施設等に寄付することは、残された子にとっても大きなメリットになる場合があります。
もちろん社会福祉法人や医療法人は全ての利用者に平等であることが基本なのですが、やはり心情が動くこともあります。
例えば、施設の利用者の親からの寄付を受け、利用者の居室(他の居室も含め)が綺麗にリフォームされた例があります。
また、大きな額になれば、新たなグループホームを建て、そこに利用者を居住させてくれたという例もあります。
そこまでの額にならなくても、職員達が感謝の想いで利用者により親切に対応してしまうというのも心情的には仕方のないことです(もちろん私が働いていた施設でもありました…)。

子の生活を保障しつつ、施設や病院に寄付をする内容の遺言例
子の生活を保障しつつ、施設や病院に寄付をする遺言の内容については、基本的には親族の場合と同様です。
施設等を遺言執行者兼全財産の受贈者にします。
そして、一定の金額を子に支払うか、子の生涯かかる費用を負担させるかを内容に加えます。
「子の生涯にかかる費用を負担させる」とは、施設に入所している当該利用者(遺言により寄付をする者の子)の生活にかかる費用を全て負担するという意味です。
遺言に記載することで法的に有効な「負担」となり、施設はその義務を負うことになるのですが、そこが曖昧であるため、財産の受け取り自体をまとめて拒否されてしまう可能性が無いわけではありません。
その場合は「負担の範囲をどこまでにしておくか」を設定しておくと良いでしょう。
ちなみに施設では、基本的生活費の他にも外泊を伴う旅行などの特別に費用がかかる催しものなどもあります。親族遺贈する場合も施設に遺贈する場合も、当該利用者が満足して生活できる費用を負担してもらうような内容にする必要があります。

子の生涯にかかる費用を計算しておく
今回の遺言の内容では、親が亡くなった後の子にかかる費用がポイントになると思います。
しかし、障害年金を受給している以上、それほど大きな額は必要としません。
実際に施設に入所していれば、毎年かかる費用は概ね把握できると思いますので、それに+αする程度で良いと思います。
なぜなら、万が一資金が底をつくようなことがあったら「生活保護」の受給ができるからです。
実は、生活保護を受給することになっても、施設の生活にはあまり影響が出ません。
今までと変わらない生活ができる場合がほとんどでしょう。
それでも不安に思う場合は、子に渡す額を増やしたり、子に財産が無くなった時の負担について遺言に言及しておくこともできます。
いずれにせよ、かなりテクニカルな内容の遺言になりますので、できる限り「公正証書遺言」で作成しましょう。
当事務所では、家族ごとの状況を踏まえる「障害者や認知症専門の遺言作成」を行なっておりますので、まずはご相談いただければと思います。
※遺贈を受ける施設や病院の方のご相談も受け付けています
遺言による寄付は、「寄付したい家族」と「寄付を受ける施設等」のそれぞれが歩み寄らなければ成立しません。
事前の打ち合わせが重要になりますし、遺言の作成や執行には法的知識も必要になります。
それでも国に財産を渡すならお世話になった施設等に寄付したいと思う方は多くいらっしゃいます。

当事務所では寄付を考えている方のみならず、「寄付をしてくれると言っているが、有効な遺言の作り方がわからない、進め方がわからない」といった福祉施設や病院からのご相談も受け付けております。