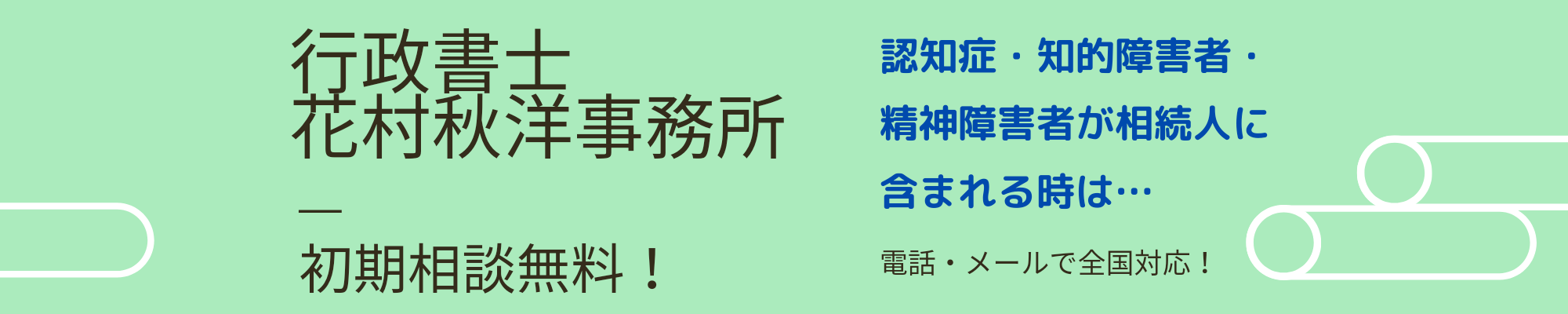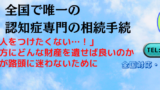認知症があっても遺言作成はできるの?
まず初めに生じる疑問として「認知症があったら遺言は作れないんじゃないの?」ということですが、認知症があっても遺言を作ることはできます。
これは今まで作ってきた実績があるからこそ言えることなのかもしれません。
例えば軽度の認知症の場合であれば、判断能力がしっかりとある方も多く、自分の財産を明確に把握し、誰に渡したいかを考えることも十分可能です。
逆に重度の方であれば、自分がどんな財産を所有しているか、誰にあげたいかなどを明確に表現することができない方が多いため、遺言が作れる可能性は低くなります。
そのため、遺言が作れる可能性は「認知症の症状により上下する」という認識を持っていただければと思います。
その認知症の症状についてですが、ご家族や施設の職員などであれば概ね把握することができると思います。
しかし外部からひと目で判断するのは非常に困難です。
その結果、多くの専門家が「認知症があるなら遺言は作れませんね」と答えてしまうのです。

優先順位は「公正証書遺言」→「自筆証書遺言保管あり」→「自筆証書遺言保管無し」
認知症があっても有効な遺言を作れる可能性があることは分かっていただけたと思いますが、遺言と言っても色々な種類のものがあります。
一般的には大きく2つ、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言は「強い」!
公正証書遺言も自筆証書遺言もどちらとも法律的に有効な遺言なのですが、事実上は公正証書遺言のほうが「強い」です。

何において強いのかというと、手続き及び裁判において公正証書遺言のほうが「強い」のです。
自筆証書遺言は遺言者自身が作りますが、公正証書遺言は自分自身では作れません。
公証人という公務員にしか作る権限がないのです。
公証人は国が行う「公証」という作業を担っています。
公証人が遺言者本人の意向を書面化し、公に認められる力を与えたものが公正証書遺言ということになります。
一方の自筆証書遺言ももちろん法律的に認められた文書です。
しかし密室で誰の関与も要せずに作成できるため、本人が作ったものか否かという点で懐疑が残ります。

そのため、裁判で覆る(無効とされる)可能性が公正証書遺言よりも圧倒的に高いのです。
自筆証書遺言も使いやすくなっているが…
また、自筆証書遺言では、様式(ルール)に沿った作り方をしないと正式な文書として認められません。
例えば日付が書かれていないだけで遺言としては無効なものとなってしまいます。
遺言として認められなければ、それは銀行でも法務局でも使えないただの「メッセージ」に成り下がってしまうのです。
そうなると遺言者や(時には)相続人にとっては大変な痛手です。
そのため新たな行政サービスとして「自筆証書遺言保管制度」というものが生まれました。
しかし自筆証書遺言は「公証」されていないため、遺言としての力は公正証書遺言には遠く及びません。
法務局の職員では法律的に力を加えることはできないからです。
そのため「保管されていない自筆証書遺言よりも少し上」ぐらいな位置付けとなります。
結果、遺言者が作るべき遺言の優先順位としては、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言(保管あり)」、「自筆証書遺言(保管無し)」ということになります。
長谷川式などの認知症検査の結果は遺言の成否に影響する?
それでは、認知症の影響が遺言にどのような影響を及ぼすのかについてですが、まず根本的な問題として「書けるか書けないか」は非常に重要です。
自分で長文が書けない状態であれば、自筆証書遺言は作れません。
しかし公正証書遺言は自分で字が書けなくても作ることができます。
そもそも公正証書遺言は自分の意志を公証人に口授し、それを元に公証人の権限で作るものだからです。
そこで問題となるのが「本人の意思能力」です。
本人の意思能力を判断するために認知症検査が有効なワケ
本人が本当に自分の意志により公証人に口授しているのか、それは公証人(証人も含む)が独自で判断することになります。
公証人とは言っても、医療や福祉のプロではありません。
そのため、はっきり言って「意思能力」については判断することができないのです。
そこで公証人が判断する際に採用したいのが「医師の意見」です。
医師が作成した診断書や意見書は非常に大きな力を持ちます。

裁判や調停などでも医師の意見が決定打となることは少なくありません。
医師がその者の認知症の程度がどれほどのものなのかを判断するために用いるのが「認知症検査」です。
認知症の検査には血液検査やCT検査が用いられることがありますが、問診形式で行える比較的簡易な検査方法もあります。
その方法には「長谷川式スケール(HDS-R)」や「WMS-R」、「ADAS」など様々なものがあります。
例えば長谷川式検査では、正しい回答ができた数によって点数を算出します。
満点は30点となり、結果が25点だったり20点だったりすれば、認知症に罹患していることを疑うわけです。

長谷川式検査などの問診型検査は、誰でも簡単に行えることを目的としている面があるため、認知症患者の家族などの非医療従事者でもある程度の水準で行うことが可能です。
そのため、受診しようかどうか悩んだ時にとりあえず家族が行ってみるということもしばしばあります。
医師または家族等が長谷川式検査などを行った結果、認知症がどの程度のものなのかが判断され、それが有効な遺言の成否に影響を及ぼすという仕組みになります。
長谷川式検査が直ちに遺言作成の成否にかからないことがある?
とここまではある程度の専門家であれば知っていることです。
しかし認知症の方の遺言作成に多く関わってきた私にしか説明できないことがあります。
それは「認知症の検査結果が直ちに遺言の成否に影響しないということも多い」ということです。
例えば先程の長谷川式検査の点数が15点だった方がいるとしましょう。
15点といえば「中程度の認知症」と診断される可能性のある点数です。

それでも有効な遺言が作成できる可能性は十分にあると言えます。
踏み込んだ発言をすれば「10点」でも有効な遺言を作れる可能性は残っていると思います。
なぜそんなことが言えるのかというと、認知症の症状が遺言内容にどれほど影響を及ぼすかはケースバイケースだからです。
遺言者自身の経歴が影響する場合
例えば長谷川式検査の点数が20点だった方と15点だった方がいるとしましょう。
前者は現役時代には物品販売営業のサラリーマン、後者は銀行勤めで相続手続部署での勤務経験が長かったとします。

それだけで遺言の内容の理解力には大きく差が開くはずです。
認知症の特徴の一つとして「短期記憶に比べて長期記憶が残っていることが多い」という点があります。
最近覚えたことよりも、かつて頭に入っていたことのほうが忘却しづらいとされているのです。
この例からも、ひとくくりに認知症検査の点数だけでは判断できず、その人全体の可能性を考えなければなりません。
遺言の内容や量が影響する場合
次は遺言自体が影響する場合です。
先程の例(長谷川式20点と15点)とした場合、前者の遺言の本文が全5ページに渡る複雑な内容であり、後者の遺言の内容が本文は「全ての遺産は次男に相続させる」という趣旨の文だけだった場合、これも遺言作成の成否に大きく影響します。

遺言にはあらゆる事項を記すことができ、財産を個別に特定の者に相続させたり、遺言執行者を定めたり、祭祀の継承者を定めたりすることもできます。
しかし内容が複雑になり、文章の量も増えることにより、認知症を罹患していると理解が難しくなっていきます。
遺言内容が分かりやすく、またシンプルであることによって理解のしやすさに大きな差が出てくるでしょう。
もう一つの重要点とは…?
認知症の方が有効な遺言を作れるのかについて、私の経験上最も重要であると考える点があります。
それは「職員の個性」です。
職員とは、法務局の職員だったり、公証人だったりと作成方法により異なりますが、私が関わる機会の多くある公証人について説明します。
公証人は全国約300箇所の公証役場に約500人ほど存在しています。
公証人も人ですから、それぞれの方に個性があるのが当然です。
となると、認知症に対しての考え方もそれぞれで異なってくるわけです。
「認知症なら遺言は作れないはずだ」というスタンスから入る方もいますし、「遺言内容に照らし合わせて本人の意志が明確に伝わるようであれば可能である」といった信念の方もいらっしゃいます。

もちろんそれでも意思能力が足りないと判断され、遺言作成が断念されることもありますが、この点について時間をかけて判断しようとしてくれる方とそうでない方では、作成可能性が大きく変わってくるのです。
諦めずにチャレンジしてみること
以上、長谷川式検査と遺言作成の可能性について説明しましたが、「長谷川式検査が低くても直ちにその点数が遺言の成否に影響しないことがある」というのを分かってもらえたと思います。
そのため、家族が難しいと判断しても、専門家が難しいと判断しても、諦めずにチャレンジすることは必要かと思います。
当事務所では、今までの経験を生かしながら、認知症の方の遺言作成について積極的に取り組んでおりますので、お困りの際はぜひご相談ください。